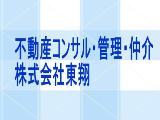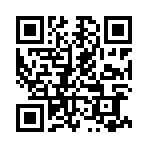2016年04月28日
離婚協議書 財産分与について
行政書士の業務において書類作成で
協議離婚における離婚協議の契約書を作成します。
離婚協議書には、いろいろな取り決めを記載していきますが、
財産分与について、今回は検討したいと思います。
夫婦の共有財産が、分与の対象となりますが、
共有財産は、婚姻後に形成された財産となり、
どちらか一方が、相続した財産や独自の能力によって
得た財産などは控除されます。
では、近い将来に得られる会社の退職金はどうでしょうか?
判例では、退職金は、給与の後払い的な意味もあるという事で
共有財産として、認められる余地があるという事です。
しかし、すべての件で対象となる訳ではなく、近い将来という
条件があります。おおよそ5年以内ではないでしょうか。
詳細は、行政書士池田健博事務所 までご連絡ください。
TEL:042-705-6197 mail:ikeda@to-syo.jp
協議離婚における離婚協議の契約書を作成します。
離婚協議書には、いろいろな取り決めを記載していきますが、
財産分与について、今回は検討したいと思います。
夫婦の共有財産が、分与の対象となりますが、
共有財産は、婚姻後に形成された財産となり、
どちらか一方が、相続した財産や独自の能力によって
得た財産などは控除されます。
では、近い将来に得られる会社の退職金はどうでしょうか?
判例では、退職金は、給与の後払い的な意味もあるという事で
共有財産として、認められる余地があるという事です。
しかし、すべての件で対象となる訳ではなく、近い将来という
条件があります。おおよそ5年以内ではないでしょうか。
詳細は、行政書士池田健博事務所 までご連絡ください。
TEL:042-705-6197 mail:ikeda@to-syo.jp
2016年04月27日
相続で失敗しない。
いざ相続が、発生した時に冷静に、対応できる人は、
そんなにいないと、思います。
今回は、遺産分割協議と相続放棄について検討します。
遺産分割の協議は、相続発生後に、相続人間で、遺産を
どのように分けるかを話し合う事です。
遺言書がない場合は、原則、遺産分割の協議を行います。
さて、相続には、単純承認、限定承認、相続放棄がありますが、
プラスの財産が多いけど、マイナスも多いいよねって言うときに、
相続の放棄をします。放棄をすれば、負債の負担が、なくなり
すっきりということになります。
では、遺産分割協議で、ある1人A氏が全て相続し、他の
相続人BC氏が放棄した場合に、借金も当然A氏が引き受けると
しました。BC氏は特に放棄の手続きましなかった場合どうなるでしょうか。
借金の債権者から、BC氏に催促があった場合には、支払い義務が生じる
可能性が高いというのが、通説です。特例で、放棄をしなかった特別の
理由が認められれば、大丈夫ですが、かなりハードルは高いようです。
つまり、遺産分割協議と相続放棄は、別の手続きで、遺産分割協議は
相続人間の取り決めで、第3者には効力がないという事で、ちゃんと
相続放棄の手続きを裁判所にしないといけないとなります。
遺産分割協議書の作成は
行政書士 池田健博 事務所 TEL042-705-6197 mail:ikeda@to-syo.jp
そんなにいないと、思います。
今回は、遺産分割協議と相続放棄について検討します。
遺産分割の協議は、相続発生後に、相続人間で、遺産を
どのように分けるかを話し合う事です。
遺言書がない場合は、原則、遺産分割の協議を行います。
さて、相続には、単純承認、限定承認、相続放棄がありますが、
プラスの財産が多いけど、マイナスも多いいよねって言うときに、
相続の放棄をします。放棄をすれば、負債の負担が、なくなり
すっきりということになります。
では、遺産分割協議で、ある1人A氏が全て相続し、他の
相続人BC氏が放棄した場合に、借金も当然A氏が引き受けると
しました。BC氏は特に放棄の手続きましなかった場合どうなるでしょうか。
借金の債権者から、BC氏に催促があった場合には、支払い義務が生じる
可能性が高いというのが、通説です。特例で、放棄をしなかった特別の
理由が認められれば、大丈夫ですが、かなりハードルは高いようです。
つまり、遺産分割協議と相続放棄は、別の手続きで、遺産分割協議は
相続人間の取り決めで、第3者には効力がないという事で、ちゃんと
相続放棄の手続きを裁判所にしないといけないとなります。
遺産分割協議書の作成は
行政書士 池田健博 事務所 TEL042-705-6197 mail:ikeda@to-syo.jp
2016年04月23日
内容証明郵便について
私たち行政書士が、行う業務の中に書類作成があります。
書類作成でも、内容証明の作成は特に重要なものとなっています。
内容証明とは、
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
当社が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。
謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人及び差出郵便局において保管するものです。
(日本郵便ホームページより)
要するに、相手方に通知を出したいが、確実に相手にいつ通知したか、どんな内容だったかを郵便局が保管してくれて
後日争いがあった時に、出しましたよという証拠のなるというものです。
そこで、争いがあった時に、いつ出したかが後日重要になって来ますので、内容証明は日付が押印され証拠となります。
クーリングオフ、契約解除、契約更新、債権の請求、などなど。
何かあった時に、そのまま何もしないというのは、かなり危険で、後日になって不利になることが多いので、
もし、自分で作成が出来そうもないなと思ったらご相談ください。
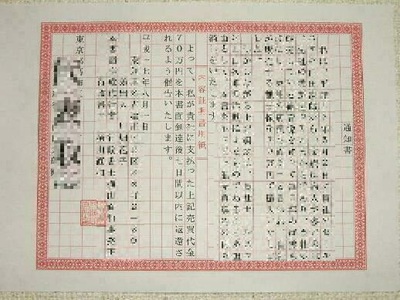
行政書士 池田健博 TEL042-705-6197 mail:ikeda@to-syo.jp